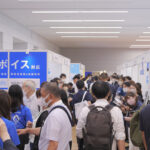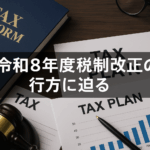最終更新日:2025-10-20
【編集長コラム】 ビットコイン高騰の陰で進む「暗号資産課税の再設計」 政府税制調査会が描く税制改革と金融行政の岐路
- 2025/10/20

2025年10月5日、ビットコイン価格は12万5000ドルを突破し、過去最高値を更新した。過去12カ月で価格が2倍となったビットコインは、「2025年で最も好調な資産」として暗号資産市場に再び注目が集まっている。一方で、税制の世界では静かな再編の動きが進む。政府税制調査会は令和7年度改正に向け、暗号資産課税の「構造的な歪み」にメスを入れる検討を始めた。国際的な課税基準との整合性、金融行政の方向転換、そして税理士・会計士の実務対応——市場の高揚の裏で、日本の制度インフラは新たな岐路に立っている。
2025年10月5日のアジア時間の取引でビットコインが最高値を更新した。米政府機関の一部閉鎖を受けたリスク資産の上昇で、世界最大の暗号資産(仮想通貨)であるビットコインを買う動きも勢いづいている。ビットコイン価格はETF承認の波に乗り、個人・法人双方で投資が再拡大しているが、それにともない税務当局も暗号資産市場に熱い眼を向けている。
暗号資産の税務処理は、基本的なルールがあるが、税の専門家である税理士に中にも詳しい人は少なくミスも多い。とくに個人で暗号資産取引するものが多く、法人においても実際の利益確定時期などで誤りやすい。
さて、現行制度では、個人は「雑所得」扱いで総合課税(最高55%)、一方で法人は期末時価評価による益金算入という異なるルールが適用される。価格変動の激しい暗号資産では、決算期をまたぐたびに評価損益が大きく変動し、実務では「未実現損益の扱い」が最大の論点となっている。
海外ではキャピタルゲイン課税が主流
暗号資産取引おいては、海外ではキャピタルゲイン課税(分離課税)を採用する国が多い。シンガポールやドバイは非課税、米国や英国は譲渡所得として扱う。国際的に見れば、日本の制度は依然として特殊な構造を抱えたままだ。
というのも、暗号資産の制度設計は、単なる税制論を超え、金融行政と財政運営が交差する領域と言える。金融庁は「市場育成と投資家保護の両立」を掲げ、取引所の登録・管理を強化してきた。一方、国税庁は「課税の公平性」を最優先に、申告制度の整備や取引履歴データの共有を進めている。そして財務省主税局は、OECDの「BEPS2.0」や「CARF(暗号資産報告枠組み)」への対応を見据え、国際的なルール整合を重視する。
この三者の立場は必ずしも一致していないのが現状だ。市場活性化を急ぐ金融庁と、徴税の透明性を求める国税庁。両者の間で、財務省が国際協調の観点から調整に入る形だ。暗号資産はまさに、縦割り行政の限界を突き付ける政策領域と言えるのだ。
政府税制調査会が注目する3つの検討軸
政府税制調査会(政府税調)が9月に公表した「資産課税等に関する検討項目」では、暗号資産の課税方法に関する明記が行われた。まだ具体的な改正案には至らないものの、次の3点が議論の中核を占めている。
①課税時期の見直し
現在は「評価時点課税」や「年またぎの時価計上」を巡り、法人・個人間で扱いが不均衡だ。実現時課税原則(売却時課税)の徹底により、取引実態に即した課税時期を明確化する方向が検討されている。
②所得区分の一本化
個人課税の雑所得方式から、株式譲渡所得に近い分離課税制度への転換も視野にある。金融所得課税一体化を進める流れの中で、暗号資産を「金融商品」に準じた枠組みに位置づける案が浮上している。
③法人課税の簡素化
現行の「期末時価評価ルール」は、実務負担が重く、海外子会社やグループ内決算の整合性を崩している。税制調査会では、期末評価義務の緩和や一定の保有目的資産の除外を検討課題に挙げた。
これらの議論はいずれも今後、税制改正項目として盛り込まれる可能性がある。すべてではないにしても、実現すれば日本の暗号資産課税は大きな転換点を迎える。
国際整合性と国内実務のはざま
OECDが策定したCARF(Crypto Asset Reporting Framework)は、各国税務当局間で暗号資産取引情報を自動交換する仕組みだ。日本は2027年導入を目標に準備を進めており、国税庁は金融庁・財務省と連携してシステム要件を整備中だ。この動きは、税理士や公認会計士の実務において影響の大きい問題だ。匿名性を前提としていた取引が、国際的に可視化される時代に入るわけで、税務上の損益計上、帳簿付け、外貨換算、さらにはブロックチェーン監査の対応範囲まで、実務の再設計が迫られる。
特に会計基準上では、暗号資産を「無形資産」または「棚卸資産」として扱うが、実務ではどちらの処理にも限界がある。評価損益をどのタイミングで認識するか、企業開示上の透明性をどう確保するか——課税と会計の整合を取る作業が急務だ。
編集長の視点 「課税の公正」から「市場の公正」へ
暗号資産の課税論は、単なる技術的議論にとどまらない。背景には、「税の公平性」を超えた「市場の公正性」という新たな軸がある。
「課税の公平」を追求すればするほど、流動性やイノベーションの芽を摘む可能性がある一方で、過度な緩和はマネーロンダリングや不正取引を助長しかねない。行政のバランス感覚が問われる局面となる。
税理士や公認会計士に求められるのは、ルールの単なる解釈ではなく、制度の「翻訳者」としての役割だ。政策意図を理解し、顧客に最適な処理と説明を提供する。そのためには、税制調査会・金融庁・OECDといった多層構造の政策議論を俯瞰的に見ていく必要がある。
市場は先を走る。制度は追いかける。だが、制度の設計次第で市場の未来は変わる。暗号資産課税の再設計は、単なる税制技術ではなく、日本の金融行政の方向そのものを占う試金石だ。「制度の静寂」が破られるとき、次の波は税務の現場から起こる。
クローズアップインタビュー
会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。
税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。