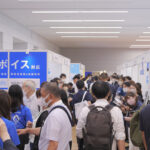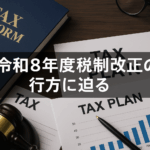最終更新日:2025-10-20
【編集長コラム】 相続税対策で生命保険はどこまで使える? 注意したい「死亡保険金」「遺言書」のポイントとは・・・
- 2025/10/22
- 2025/10/20
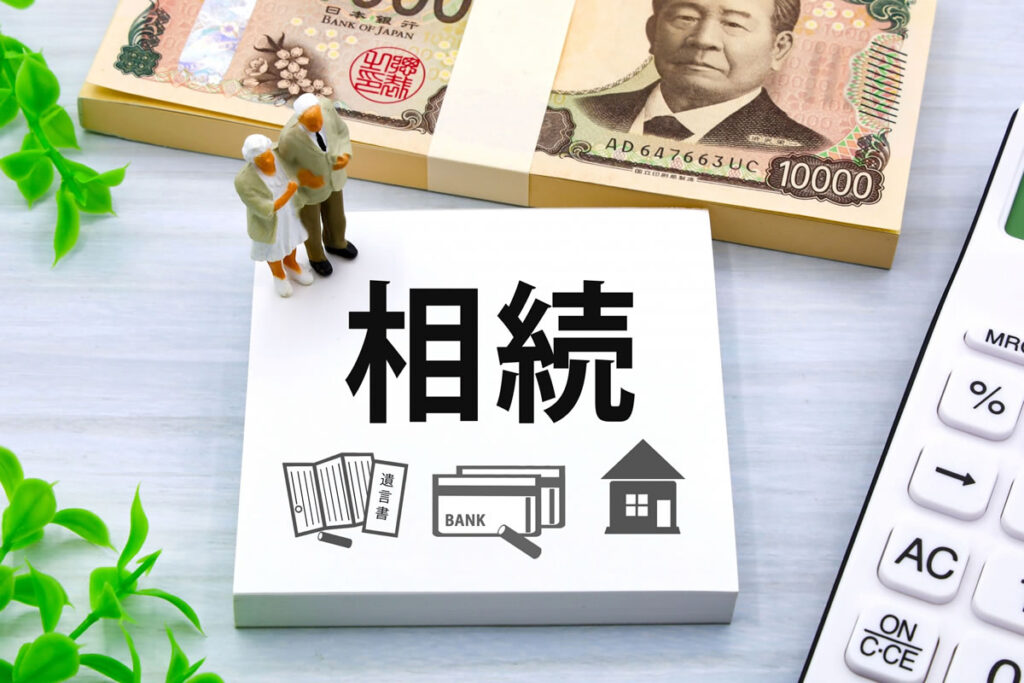
日本は今、未曾有の高齢化社会を迎えている。内閣府の「令和6年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の人口は全人口の3割近くを占め、死亡者数は今後さらに増加すると推計されている。平均寿命の延伸は喜ばしい一方、人生の最終局面において「財産を誰に、どのように残すか」という課題は避けられない。特に夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者が安心して暮らせるようにするための制度設計が重要だ。その際にカギを握るのが「生命保険」と「遺言書」、そして「節税」である。
日本政府は1990年時点では、65歳以上の「高齢者」が人口の12.1%を占め「高齢社会」と分類していたが、2000年には18.0%、2010年には23.0%に達し、「超高齢社会」へと発表するようになった。
2025年には団塊世代が75歳以上となり、75歳以上人口が全体の約18%を占める見込みである。2020年には高齢化率28.6%、2025年には29.4%に達し、2040年には35%、2050年には37.5%に達すると推計されている。
総人口は1990年の約1億2,300万人から減少傾向にあり、2050年には1億人を下回る可能性もある。高齢者人口の増加と出生率の低下により、人口構造は大きく変化し、社会保障制度や労働力確保に対する課題が一層深刻化する見通しである。
こうしたなか、おちおちしてられないのが相続問題だ。お金が絡んでくるため、生前に本人を前に話をするのは引けるが、亡くなってからでは、親族間で揉めることが多いのが現実。それも、相続財産を何億円、何十億円も持っている富裕層より、一般的な家庭で、自宅を所有し、幾らかの現金を持っていたケースだ。こうした場合、相続財産をどう分けるか、また、節税を考えた相続ということも真剣に考えておく必要がある。
生命保険金は遺産か?
「自分が死んでも配偶者には、生活できるお金の残したい」と考え、生命保険に入っている人は多いと思う。そのばあい、例えば、夫が被保険者で、保険料の支払いも夫自身が行い、受取人を妻に指定しているとする。この場合、夫の死後に支払われる死亡保険金は遺産分割の対象になるのだろうか。
結論から言えば、妻が受取人である以上、その保険金は妻の「固有財産」であり、遺産には含まれない。民法上、生命保険金は契約に基づき、受取人固有の権利として取得されるからだ。したがって、夫が遺言書を作成する際に、あえて保険金の扱いを記載する必要はない。
しかし、相続税法では死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象に含まれる。民法では遺産に含まれないが、税法では課税されるのだ。この二重構造が誤解を生みやすく、「保険金は遺産ではないから相続税もかからない」と考える人も少なくない。実際には相続税の計算に組み込まれるため、節税の視点が欠かせないのだ。
遺言で受取人を変えられる?
生命保険の受取人は、契約者と保険会社の合意により変更できるが、遺言書による変更も可能だ(保険法44条1項)。ただし、保険会社の約款で受取人の範囲は制限されることが多く、配偶者や子どもなど一定の親族に限られるのが一般的だ。
遺言で受取人を変えたい場合は、自筆証書遺言や公正証書遺言など、法的要件を満たす必要がある。不備があれば無効となる可能性もあるため、専門家の助言を受けながら作成するのが望ましい。
遺言書は被相続人の意思を反映するものだが、生命保険金については必ずしも記載する必要はない。保険契約によって受取人が指定されているため、法律上は契約内容が優先されるからだ。
もっとも、実務上は「妻に保険金を生活費に充ててもらいたい」といった希望を遺言に記しておくことで、相続人間の理解を得やすくなる。法的効力はなくても、家族への「メッセージ」として有効だ。
節税のための2つの非課税枠
夫が亡くなった場合、妻が受け取る死亡保険金には相続税がかかるが、ここで重要になるのが非課税制度である。
第一に「生命保険の非課税枠」。これは
500万円 × 法定相続人の数
が非課税となる制度である。
例えば妻と子2人が法定相続人なら、
500万円×3人=1500万円
まで非課税となる。
第二に「配偶者の税額軽減」、いわゆる1億6千万円の非課税枠だ。
妻(または夫)が相続する財産については、①法定相続分相当額、または②1億6千万円のいずれか多い額まで相続税がかからない。この特例は、残された配偶者の生活保障を第一に考えたもので、相続税制度の中でも最大級の優遇措置といえる。したがって、夫が妻に財産を残す場合、生命保険金の非課税枠と配偶者の税額軽減を組み合わせれば、相続税の負担を大きく減らすことが可能だ。実務的には、妻にある程度の財産を集中させ、子どもへの分配を二次相続(妻の死亡時)に回すという設計が有効になるケースも多い。
高齢化と「争族」リスク
ただし、注意が必要なのは税制上の得失だけではない。死亡者数の増加に伴い、相続をめぐる「争族」トラブルも増えている。保険金は妻の固有財産であるため、子どもたちが直接分け前を主張できない。しかし、遺産全体の配分に不公平感があれば、感情的対立が生じかねない。
特に「妻に全財産を集中させた場合」、二次相続のときに子どもが多額の相続税を負担するリスクもある。このため、単に非課税枠を最大限利用するだけでなく、二次相続も見据えた分割と節税設計が求められる。
高齢化が進む現代において、夫が妻にどう財産を残すかは家族にとって避けられない課題だ。生命保険は「遺産ではないが課税対象」となる特殊な位置づけを持ち、遺言との関係も理解しておく必要がある。そして何より、妻には1億6千万円までの大きな非課税枠が認められている。この制度をどう活用するかが、残された配偶者の生活と家族の安心を大きく左右する。
財産の承継は、単なる節税テクニックではなく、残された家族の将来を支える設計である。保険金、遺言、非課税枠。この三つをどう組み合わせるかを真剣に考えることが、いま私たちに求められている。
クローズアップインタビュー
会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。
税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。