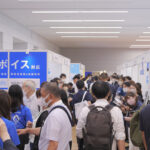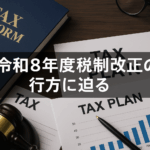最終更新日:2025-10-16
特集 マイナンバーカード一本化の行方 国税庁「GSS」導入で進む連携と、拭えぬ情報流出リスク
- 2025/10/16

国税庁は2025年10月1日より、e-Tax申告における「ID・パスワード方式」の新規発行を停止し、マイナンバーカード方式への一本化を本格化させた。背景には、デジタル庁が推進する「ガバメントソリューションサービス(GSS)」による行政システム統合がある。しかし、外部連携が進むほど、サイバー攻撃や情報流出のリスクも増す。利便性と安全性――行政デジタル化の“光と影”が問われている。
これまでe-Taxでは、マイナンバーカードを持たない納税者にも暫定措置として「ID・パスワード方式」が認められていた。しかし、マイナンバーカードの保有率が8割を超えたことを受け、国税庁は同方式の新規発行を停止。今後はマイナンバーカードを用いた本人認証方式へと一本化される。
国税庁は「本人確認の厳格化と手続き効率化の両立」を目的とするが、背景には単なる認証方式変更にとどまらない「行政DX」の潮流がある。
それが、デジタル庁が推進する「GSS(ガバメントソリューションサービス)」の導入だ。
GSS導入と「データ連携社会」への転換
GSSとは、政府共通のクラウド基盤で各省庁システムを運用・連携させる仕組みだ。
これにより、国税庁を含む各機関のデータが統一仕様で扱われ、行政間・民間間の情報連携がスムーズになる。例えば、マイナポータル経由で医療費控除情報を自動取得する、銀行口座情報と税務情報を連携させる――といった仕組みもGSSの中核にある。つまり、マイナンバーカード一本化は、単なるe-Tax操作の変更ではなく、行政データ全体の「クラウド連携時代」への入口にあたる。だが、便利になる一方で、「情報が外部と接続される」という構造が、まさに新たなリスクの温床にもなり得る。
GSSによって、従来は閉じられた官庁ネットワークがクラウド経由で外部とつながることは、行政サービスの迅速化に不可欠だが、同時に「攻撃対象が増える」ことを意味する。実際、国内外では官公庁を狙ったランサムウェア攻撃が急増。2024年には大手飲料メーカーのサントリーが海外拠点でハッカー攻撃を受け、内部情報が流出する事件も発生した。このような事案は、もはや企業だけでなく、政府機関にも他人事ではない。
クラウドを介した外部連携は、利便性と引き換えに「一箇所を破られれば全体に影響する」リスクを孕む。行政が持つ情報の中には、個人の所得・資産・健康情報など極めて機微なデータが含まれる。それらが一度でも外部に流出すれば、信頼は一気に失墜する。
技術的防御と制度的ガバナンス
国税庁は「暗号化通信、多要素認証、分離ネットワークなどで安全性を確保している」と説明する。だが、サイバー攻撃の多くは「ヒューマンエラー」「委託先の脆弱性」を突いてくる。サントリーのケースも、技術的防御をすり抜けた「認証情報の外部流出」が発端だったとされる。
行政システムも例外ではなく、GSS導入によって委託・管理層が広がる分、統制の難しさは増す。技術的な防御に加え、情報アクセス権限の厳格化、ログ監視、外部監査など、制度的なチェック体制の再設計が不可欠だ。
デジタル庁が唱える「安全・安心な政府クラウド」は、運用体制が伴ってこそ現実のものとなる。会計事務所にとって、マイナンバーカード方式への一本化は、顧問先対応の大きな転換点となる。
これまでのようにID・パスワードで即時発行・即申告という簡便さは失われ、カード取得支援やスマートフォン連携支援が必要になる。また、マイナンバーカード情報を扱う以上、事務所内の情報セキュリティ管理も再点検が求められる。
会計事務所などは、顧問先のカードを預かる行為や暗証番号の聞き取りは厳禁であり、「便利さの裏にある責任の重さ」がより明確になる。
「一本化」は本当に安全なのか
マイナンバーカードの一本化は、行政の効率化と国民の利便性を大きく前進させる。
だが同時に、デジタル社会の基盤としての「信頼性」をどう担保するかという根本的な問いを突きつけている。GSSによるクラウド統合は避けられない流れだとしても、それは新たな“入り口”を作ることでもある。利便性とリスク、効率化と安全性――この二律背反の中で、どこに均衡点を見出すのか。行政のデジタル化が加速する今こそ、私たちは改めて問わなければならない。マイナンバーカードへの一本化は、本当に安全な選択なのか・・・
クローズアップインタビュー
会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。
税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。