最終更新日:2025-09-10
接待交際費 中小企業が押さえておくべき損金算入のポイント 会議費との境界線に注意
- 2025/09/12
- 2025/09/10
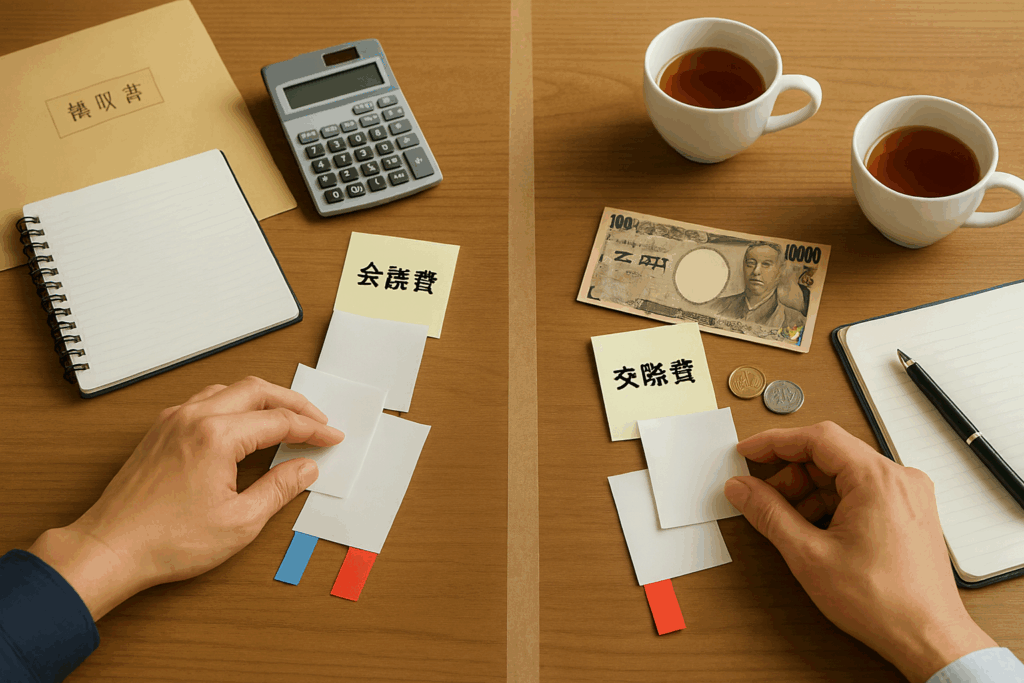
国税当局の令和7年事務年度(2025年7月~2026年6月)がスタートし、税務調査も本格化している。税務調査で一番チェックされる一つに「接待交際費」だ。とくに、オーナー経営者の場合、「会社のお金は自分のお金」という感覚がある。また、社員にとっても営業手段として接待は欠かせない。ただ、税務上、慎重な判断が求められる領域だ。2024年4月の税制改正により、1人当たりの飲食費基準が1万円に引き上げられ、会議費との区分がより重要になった。特に資本金1億円以下の中小法人では、損金算入の特例を活用することで節税効果を得られる一方、誤った処理は税務調査リスクが高まる。国税庁の最新指針と実務上の注意点を踏まえ、税理士・経営者が知っておくべき交際費の取り扱いと戦略的活用法に迫った。
法人が事業に関係する者に対して行う接待、供応、慰安、贈答などの行為に要する費用は、税法上「交際費等」として定義される(国税庁 No.5265)。これには、飲食費、贈答品、会合費などが含まれるが、原則、損金不算入、つまり税務上の経費として認められない。ただし、法人の規模に応じて一定額まで損金算入が認められる特例が設けられており、特に中小法人(資本金1億円以下)にとっては合法的な節税ポイントだ。
中小法人の損金算入特例の2つの選択肢
資本金1億円以下の法人は、以下のいずれかの方法で交際費の損金算入が可能だ。
- 年間800万円までの交際費を全額損金算入
- 接待飲食費の50%相当額を損金算入
この「接待飲食費」とは、取引先等との会食に要した飲食費を指し、贈答品(お中元・お歳暮等)は含まれない。どちらの方法を選択するかは法人の任意だが、年間の交際費が800万円以下であれば、定額控除方式の方が有利なケースが多い。
一方、800万円を超える場合は、接待飲食費の50%方式を選ぶことで、より多くの金額を損金算入できる可能性がある。
2024年改正で1人当たり「5千円」→「1万円」基準”へ
2024年4月以降、接待飲食費の判定基準が「1人当たり5千円」から「1万円」に引き上げられた。これにより、以下のような支出は交際費ではなく「会議費」として処理が可能だ。
例えば、取引先を含め4人で飲食し、合計金額が3万円 → 1人当たり7500円 → 会議費として処理可能
同改正により、実務上の柔軟性が増し、節税効果も期待できる。会議費として処理すれば、損金算入の上限に縛られず、全額経費として認められる。交際費枠を温存する戦略が可能となる。
会議費と交際費の判断ポイント
取引先との打ち合わせを会議費として処理するためには、以下の条件を満たす必要がる。
- 取引先との会議や打ち合わせの目的が明確であること
- 飲食が会議の一環として提供されていること
- 一人当たりの飲食費が1万円以下であること
- 議事録等、参加者の情報が保存されていること
取引先との会議における会議費は2014年以降、一人当たり1万円以下が条件だが、全額損金算入が可能となり、交際費の枠を超えた支出を吸収する手段として有効だ。ただし、税務調査では「実態」が重視されるため、形式的な処理ではなく、実際に会議が行われたことを証明できる資料の整備が不可欠だ。
オーナ社長はプライベート支出との区別が不可欠
交際費の処理において最も注意すべきは、事業関連性のない支出の混入だ。例えば、オーナー社長個人の友人との会食、家族との飲食、趣味仲間との懇親などは、基本的には、たとえ会社名義で支払っていても、税務上は損金算入が認められない。
税理士としては、顧問先に対して「交際費台帳」の整備を促し、支出目的・参加者・金額・場所などを記録する体制を構築することを指導する必要がある。
交際費は節税だけでなく営業戦略上の重要な経費
交際費は単なる支出ではなく、営業活動や関係構築の投資でもある。特に税理士をはじめとした士業、不動産業、コンサルティング業など、人的ネットワークが業績に直結する業種では、交際費の活用が戦略的に大きな意味を持つ。ただし、過度な支出は税務リスクだけでなく、社内のガバナンスにも影響する。経営者は、交際費の「費用対効果」を意識し、社内規定や承認フローを整備することで、透明性と健全性を確保する必要がある。税理士は、顧問先機に対して、業種・規模・収益構造に応じた交際費の「適正水準」を提案し、経営者と共有することで、税務対応と経営判断の両面から支援することができる。
クローズアップインタビュー
会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。
税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。




