最終更新日:2025-11-12
相続税調査もAIの時代へ──国税庁「RIN」が導く調査とは!?
- 2025/11/13
- 2025/11/12
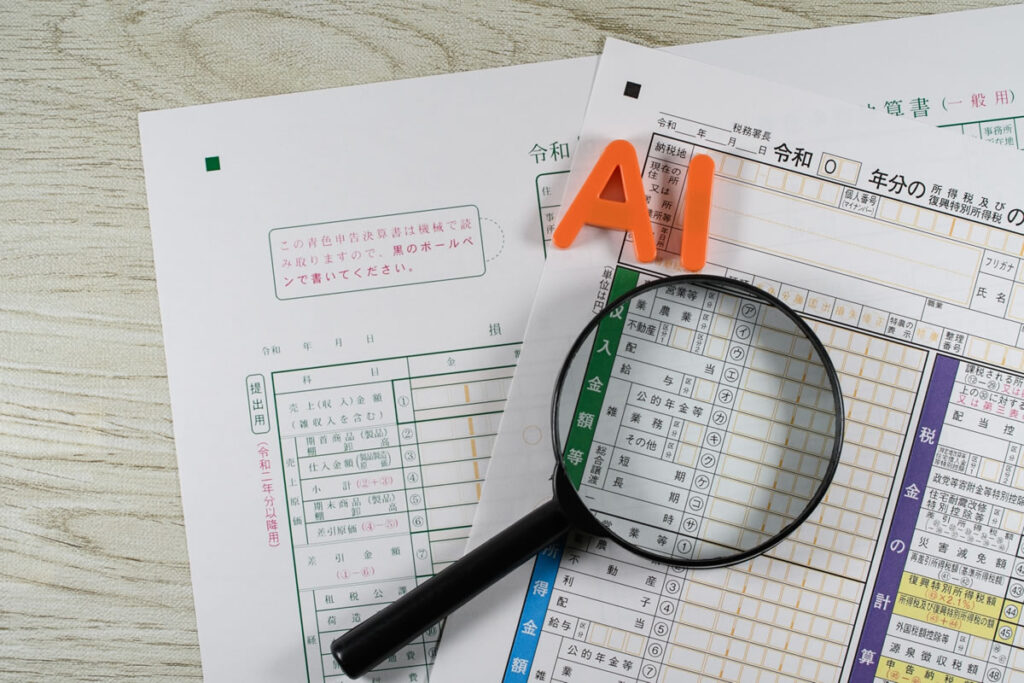
国税庁は2026年度を目標に、相続税調査の要となる調査対象選定業務の大半をAIに移行する方針を明らかにした。少子高齢化による人手不足を補い、より公平で効率的な税務行政を実現する狙いだ。中核を担うのは、国税庁の基幹システム(KSK)と連携する相続税選定支援ツール「RIN」。AIが膨大なデータを分析し、申告漏れや不正リスクを可視化する「新時代の税務調査」が幕を開ける。
相続税調査に迫る「AI時代」の幕開け
2023年度の相続税収は3兆円を突破し、課税件数割合(年間課税件数を死亡者数で割った割合)は1割目前まで上昇した。高齢化の進展で今後も増加が見込まれるなか、国税庁は相続税調査にAIを導入し、調査の精度と公平性を高める構想を進めている。
これまで調査対象の選定は、ベテラン調査官が資産規模や申告内容の異常値を基準に選ぶのが通例だった。典型的な例が「名義預金」や「名義株」だ。
例えば、夫の扶養に入っている妻名義の高額預金や、父親の資金で子の名義口座が運用されている場合など、実質的な贈与・相続とみなされるケースが多い。
しかし今後は、調査官の経験や勘に頼る手法から脱却し、AIが申告データや不正パターンを分析して調査先を特定する仕組みへと転換する。国税庁は2026年度を目標に、「調査先選定はAI」「実地調査は人間」という明確な役割分担を打ち出している。
「RIN」──相続税AI調査の中核ツール
AI導入の中心となるのが、KSK(国税総合管理システム)と連携する「相続税選定支援ツールRIN」だ。国税庁は税目別にAI活用ツールを整備しており、所得税では「SAT」、法人税では「結(ゆい)」がすでに稼働している。RINはその資産税版にあたる。
その基幹システムKSKは、今後、次世代システム「KSK2」にバージョンアップしていく。国税庁より情報公開した内部資料によれば、KSKとKSK2との大きな違いは二つ。
一つ目が、政府が進める「ガバメントソリューションサービス(GSS)」との連携だ。デジタル庁によれば、GSSは府省などの行政機関の業務用PCやネットワーク環境などの業務実施環境を、政府共通の標準的な環境として提供するサービスとしている。府省 LAN 統合として高度化する脅威に対応したゼロトラストアーキテクチャに基づき、利便性とセキュリティ両面を確保したネットワークへの統合を進める基盤というわけだ。人事院及び各府省庁は、2022 年度(令和4年度)以降のネットワーク更改等を契機にこの環境へ移行する。つまり、国はGSSをベースに各省庁を超えた共通インフラの基盤作りを進めているわけだ
二つ目が、国税当局における税目を超えた情報共有だ。
現在、国税当局は、法人税や所得税など、税目を超えた横の連携はしておらず、各部門で情報を管理している。典型的な縦割り行政なのだ。これをKSK2では、部門を超えて情報共有できるようにしていく。そして、税務申告に関する情報だけでなく、各省庁、民間データ等をKSK2に蓄積して、税務調査等に活用していく。
令和6年5月17日に開催された全国国税局調査査察部長会議資料によれば、「令和7年以降、順次GSS環境へ移行し、KSK2導入までに移行を完了する予定(中略)。DXを推進する観点から、KSK2・GSS導入を見据えて各種検討を進めていく必要がある」としている。
これまでRINは、調査官がKSKデータから問題点(条件)を入力し、一般値との比較で異常値を検出する“支援ツール”として使われてきた。検出結果を統括官(民間企業で言う課長級)が検証し、必要に応じて調査対象を決定するという流れだ。
しかし現在は、統括官らのノウハウをAIに学習させる取り組みが進行中である。プログラミング言語をPythonからTableauへ移行し、分析手法もより高度な統計解析型モジュールに切り替えた。これにより、AIが自動的に過去の申告漏れ事例や不正傾向を抽出し、確率的にリスクを予測できるようになった。
さらに、RINはKSK2への移行を見据えてリスクスコアリング機能を強化中だ。AIは過去の相続税事案を学習し、申告ミスや不正発生の条件を分析。納税者ごとに「申告漏れリスク」をスコア化し、A〜Dランクで分類する(Aが最もリスクが高い)。
データ統合で変わる調査フロー
RINは申告書のほか、以下のような多様な情報ソースを統合して分析する。
- 生命保険金や地金取引の支払調書
- 一定規模以上の資産を持つ人の財産債務調書
- 海外送受金データや証券口座情報
これらをAIが照合し、追徴税額の見込みや不自然な資金移動を基に調査優先順位を算出。従来は人が数週間かけて行っていた分析を、AIが数時間で完了できるとされる。
国税庁は将来的に、「AIによる分析は本庁で実施し、実地調査は国税局・税務署が担当する」という二層体制を確立する計画だ。これにより、経験の属人化からデータ主導の公平な選定へと進化する。
公平性と効率性の両立
AI導入によって最も注目されるのが、調査の公平性向上だ。
従来の相続税調査は、数億円以上の資産を持つ富裕層に集中しがちだったが、AI導入後は、資産規模に関わらず申告内容のリスクを基準に調査先を決定する。つまり、「金額は小さくても、ミスや不正があれば調査対象になる」時代に入る。
国税庁は「AI等の分析による的確な選定を通じ、大口・悪質な不正が想定される納税者に重点的に事務量を投下する」としており、従来よりも精度の高いターゲティング調査が可能になる見通しだ。
e-TaxとDX化の相乗効果
AI活用を支える基盤整備として、国税庁はe-Taxの拡充に力を入れている。法人事業概況説明書や勘定科目内訳明細書などの添付書類は、XML・XBRL・CSV形式での電子提出が推奨され、イメージデータ(PDF等)での提出は不可となった。
これは単なる利便性向上策ではなく、KSKシステムにデータを取り込みやすくし、AI分析を強化する狙いがある。
さらに、金融機関等への反面調査のオンライン照会など、関係機関との情報共有のデジタル化も急速に進んでいる。
2023年6月公表の「税務行政の将来像2023」では、照会・通達業務のオンライン化を正式に制度化する方針が示された。
会計事務所が取るべき次の一手
国税庁のAI戦略は、「申告・審査・調査」のすべてをデータで連動させる税務DXの中核プロジェクトといえる。
会計事務所にとっても、AIが調査選定を担う時代に備え、次の点が重要になる。
- 電子申告データの正確性確保と、形式面での整合性チェック
- e-Tax対応システムの更新・自動化の早期対応
- 顧客資産データの透明性確保と記録管理体制の見直し
A I化の進展は、調査の厳格化というより、透明で公平な税務環境を実現するための転換点だ。国税庁が掲げる「データとAIによる新しい税務行政」の実現には、民間側の理解と協力も不可欠である。
<出典: 国税庁「令和6事務年度資産課税部門における事務運営(全管特別国税調査官・資産課税部門統括国税調査官会議資料)」、「税務行政の将来像2023」より。
クローズアップインタビュー
会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。
税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。




