最終更新日:2021-05-21
融資の「否決」と「取り下げ」の違いは天と地の差があります
- 2021/05/14
- 2021/05/21
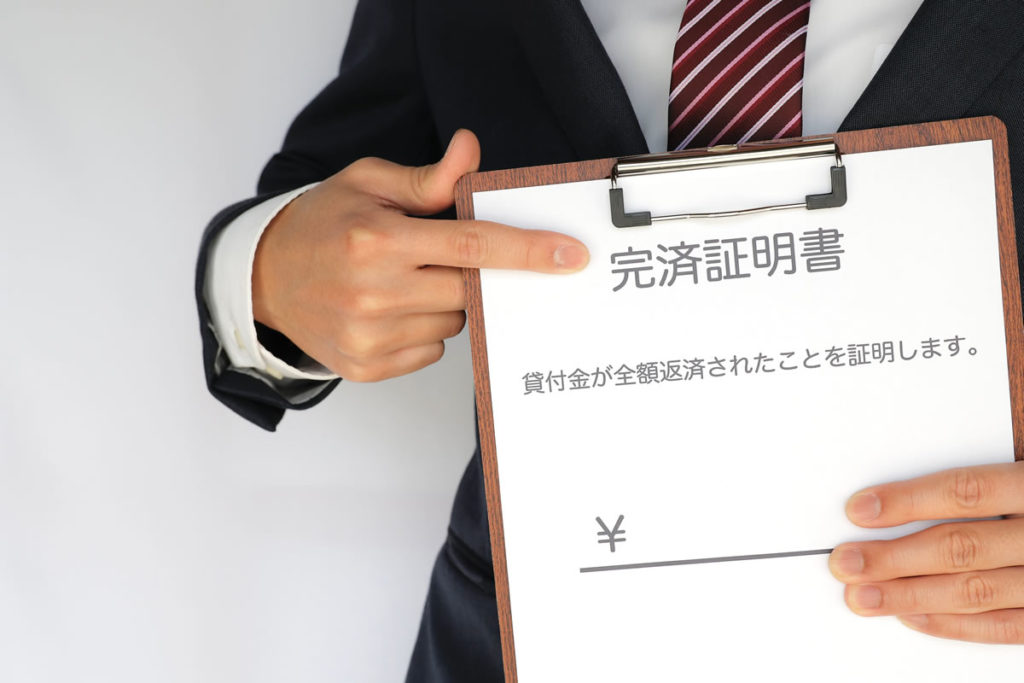
監修者

徳永 貴則
(株)スペースワン 代表取締役 金融税理士アドバイザー講座主宰
大和銀行(現りそな銀行)にて、都内を中心に主に法人融資の新規開拓業務を行う。その後、本店融資部・審査部門を歴任。2,000社以上の融資に携わる。これらの経験を活かし㈱スペースワンを創設。銀行融資のコンサルをはじめ、事業再生や経営改善のアドバイスも行っている。
また、金融税理士アドバイザーの専任講師としても活躍中。
政府がコロナ特別融資の「無利子・無担保」上限額を4千万円→6千万円へ引き上げると発表しました。
日本政策金融公庫・民間銀行での保証協会保証融資ともに上限額が引き上げられます。
本件でのお問い合わせや質問を頂くのですが、根本的なところで「そもそも全ての企業に対して融資枠が引き上げられたのではなく、無利子・無担保の範囲が拡大された」のです。
つまり、1回目のコロナ融資が受けられた企業が全て2千万円の枠が供与されたことではないことをよく理解して欲しいと思います。
大切なのは
①この1年ほどの間にどんな対策を打ってきたのか?
②2回目のコロナ融資を含めて既存の借入金を返済できる絵が描けるのか?
になります。
前回も申し上げましたが、負債の増加に目をつぶり、手元キャッシュを増やす時期は終わりました!
6千万円の拡大が「生き金」になる企業にしかこの制度は使うべきではないと私は思っております。
金融機関に融資を申し込んで、審査の結果、「融資の決裁がおりませんでした」と回答された経験がある方もいると思います。
金融機関の人が融資を断る場合には、内部では2つの処理方法があることを皆さんはご存じでしょうか?
今回は、残念な話ではありますが、融資が断わられた場合の内部処理方法のお話をさせて頂きます。
「取り下げ」とは何か?
「取り下げ」とは融資審査を申し込んで後に、担当者が稟議を起こし、上席に承認を得る過程で、貸出先に難がある(財務内容や他行の動向などなど)ことから、融資が出来ないと判断した場合に、その稟議が「なかったことにする」ことを言います。
銀行によって取り扱いが違うかもですが、私の経験では稟議の発行番号を取り消して、稟議の記録を無くしておりました。
ただし、融資の申し込みや相談はあったことや内部で議論した記録は残しておきます。
下記に挙げている「否決」との大きな差は、まだ次の融資を審査をするチャンスはある!ことです。
「取り下げ」とは今回はご縁がなかったけども、企業側も努力の結果を残してくれれば、後日、また改めて審査はできる制度です。
「否決」とは何か?
一方、「否決」とは「次の融資のチャンスは二度とない」点が前述の「取り下げ」と大きく違う点になります。
では「否決」とはどういったときに起きるのか?
私が経験したことであるのは案件が本部決済になる稟議の場面が多かった記憶があります。
本部稟議とは担当の支店の支店長まで回付され押印された稟議を、改めて本部で審査協議することは皆さんもよくご存知だと思います。
本部で審査するなかで、「本部としてはどうしてもOKが出せない!」場合に、支店と本部で言い争いになり、支店としての立場を強く押すため?
(支店長のプライドもありそうですが)に「この稟議は本部で否決扱いにしてくれ」と指示されることがあります。
また、金融機関としては融資が難しいと判断しているにも関わらず、取引先があまりにしつこく食い下がる場合に記録を残すために敢えて「否決」の手段をとる場合もあります。
否決の場合は、起こした稟議は残りますし、「否決」された記録もずっと残ることになります。
(言い方は悪いですが、その取引先は融資取引先は「出禁先」となります。
よく銀行員は「総合的に判断して無理でした」とのフレーズを使いますが、少しでもダメだった理由を聞き出すことが、今後何を改善していかないといけないか?のヒントになります。
「否決」扱いにすることはそんなに多くないことではありますが、皆さんでもし融資が断られた場合には、可能な限り融資がダメな理由を具体的に聞かれることをお勧めします。
クローズアップインタビュー
会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。
-300x200.jpg)

-8-300x200.jpg)


税界よもやま話
元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。









